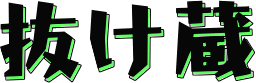24系「銀河」


東京~大阪を結んでいた寝台急行が「銀河」です。
「きたぐに」とともに数少ない、そして最後の寝台急行でした。「最終の新幹線・航空機より遅く出て、始発の新幹線より早く着ける」というビジネス需要に振り切ったような列車でしたが、2008年3月改正で廃止されています。
写真は朝の大船駅で373系と並ぶ「銀河」。機関車側にはヘッドマークがつかない、珍しい寝台列車でした。


テールマーク(左/上)と行先表示(右/下)の様子。
「銀河」はJR西日本所属車で運行されていたため、行先表示はJR西日本車の体裁でした。
撮影日時・場所
撮影日:2005年4月11日、2005年12月
撮影場所:「銀河」 東京駅 車内
備考
この写真を撮影した2005年当時、私はまだ義務教育期間中だったため、写真の質についてはお許しください。
A寝台


大阪方先頭の1号車に連結されていた、開放型A寝台車。
「中央に通路+左右にレールと平行に寝台」のプルマン式で、この列車のほか>>「日本海」(大阪~青森:2012年廃止)でも見られました。


A寝台下段の様子。
浴衣とハンガーのセットは定番ですが、スリッパはB寝台の常備品と異なり、白い紙製の使い捨てのもの。これがB寝台とのささやかな「差別化」でした。
上下幅こそ1120mmありますが、寝台幅は930mm。寝台幅に限っては583系のB寝台下段より70mm狭いですが、そこをツッコむのは無粋というものです(→「備考」参照)。
【備考:A寝台はやっぱりA寝台】
銀河のB寝台下段の料金は当時6,300円、対するこのA寝台下段は10,500円でした。1.5倍以上の寝台料金を支払うに相応しかったかは別にしても、「銀河」の中では一人当たりの専有面積がダントツに広かったです。
これがA寝台としての「格」というか、「矜持」なのでしょう。


上段寝台の様子(左/上)と、寝台番号のプレート(右/下)。
上段寝台には、583系でも見られた小型ののぞき窓が。寝台幅は880mm、上下幅は920mmと下段寝台より劣るのは否めません。そのためか、寝台料金も下段の10,500円より安い9,540円となっていました。
A寝台 喫煙スペース


A寝台入口の喫煙スペースの様子(左/上)と、座席のアップ(右/下)。
このスペースはA寝台の利用者専用となっており、B寝台の利用者は最初から喫煙号車を予約するか、喫煙号車に行って通路で吸うよう案内されていました。
B寝台

変わってB寝台の様子。
開放型B寝台は寝台モケットの更新以外、大きく手を加えられた形跡はありませんでした。


下段寝台のアップ(左/上)と、私が乗車時にリネン類をセットしてみた様子(右/下)。


上段寝台の様子(左/上)と、B寝台の常備品スリッパ(右/下)。
おまけ


通路突き当たりの様子(左/上)と、減光前の通路の様子(右/下)。
当時運行されていた「はやぶさ」「富士」「北斗星」などは、乗車してから就寝時間までそれなりに時間があったことから夕餉の時間~晩酌の時間があり、乗り合わせた乗客同士での交流が楽しめた列車でした。
対する「銀河」は所要時間が短いためか、“乗車したら速攻寝る”という利用者が多く、下り大阪行きでは、横浜を出たらすぐに通路は静まり返っていた記憶があります。今思えば、これも「銀河」ならではの“表情”だったのかもしれません。
概説
デビュー年:1972年(車両)
寝台列車の主力車両。当初B寝台は3段式で登場したが、その後寝台列車の需要減少や設備改善のために、現在は全てが2段式になっている。
車体構造はその前に登場した14系とほぼ同様だが、1972年11月の北陸トンネル火災事故の教訓をきっかけに防火対策を強化したほか、電源は集中電源式が使用されている。