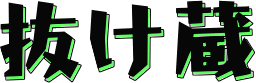14系15形 「富士」「はやぶさ」「さくら」


東京~九州を結ぶブルートレインは、21世紀に入ってもしばらくは数本が残っていました。
2005年までは、「はやぶさ」「さくら」が東京~鳥栖間で併結運転(1998年開始)をしており(写真左)、「さくら」の廃止後は「はやぶさ」「富士」が併結運転に(右写真)。併結相手が変わるたびに、それぞれ専用のヘッドマークが用意されていました。
しかし、最後の生き残りだった「富士」「はやぶさ」も、利用者減少と車両の老朽化には抗えず、それぞれ2009年3月で廃止。同時に、20系の時代から続いた「九州ブルトレ」の歴史に、完全に終止符が打たれています。
さて、このページでは最末期の「富士」「はやぶさ」(+「さくら」)で使用されていた14系15形を取り上げます。当時は細かいところまで車内を撮影しておらず、掲載枚数は少ないですが、資料の一つとしてご覧いただければ幸いです。


「富士」の大分駅でのカット(左)と、「はやぶさ」の行先表示(右/下)。JR九州所属のブルートレインは、国鉄時代からの行先表示を最後まで残していました。
モケット


(左)B寝台 (右)A寝台
撮影日時・場所
撮影日:2007年1月・12月・2008年10月ほか
撮影場所:「富士」 横浜駅 車内ほか
備考
当列車で使用されていた客車が保存されている>>ブルートレインたらぎ(ソロ)、>>阿久根ツーリングSTAYtion(現オハネフの宿:開放型B寝台)の項も併せてご覧ください。
A寝台「シングルデラックス」(※「さくら」は非連結)


まずは「はやぶさ」「富士」での最上位クラスだった「シングルデラックス」から見ていきます。(左/上)が外観、(右/下)が通路の様子です。
この車両は、いわゆる開放型B寝台からの改造車。そのため、窓割こそ個室に合わせて変更されているものの、廊下にはB寝台時代の面影が垣間見えるのが面白いところでした。
「富士」「はやぶさ」は2005年3月までは24系25形により運行されており、このシングルデラックス車も元々24系25形から改造された「オロネ25形」でした。
しかし2005年3月以降、「富士」「はやぶさ」の使用車両を(「さくら」廃止で余剰となった)14系15形に置き替えることとなり、シングルデラックス車は2005年1~2月の間、一時的に編成から抜かれて24系→14系化の改造を実施。2005年3月改正以降、「オロネ15形」として14系15形に編入され、運用に復帰しました。

個室に入ります。JR九州所属の「シングルデラックス」はJR九州への移行後、1990年代前半頃に内装のリニューアル工事を受けています。
目につくところでも「化粧板の木目調化」「寝台モケットの交換」「コート掛けを金色に変更」などの違いが見られます。木目調に金色の組み合わせは、やや“バブリー”な雰囲気すら感じますが……これは改造された時期のトレンドだったのでしょうか。


寝台のアップ(左/上)と寝具類の様子(右/下)。
備え付けの浴衣は、通称「工柄」と呼ばれる柄です。これは、読んで字のごとく「工」を組み合わせた模様で、国鉄時代から存在した“由緒”ある柄。JR九州・JR西日本ではブルートレインの完全廃止まで、この浴衣が提供されていました。
ハンガーの「九鉄リネン」の文字も、九州ブルトレではもはや“定番”です。
JR九州所属の寝台車には、必ず「九鉄リネン」のハンガーが載っていました。幼い頃の私はこれを見て「あぁ、この車両は本当に九州から来たんだ」と、妙にしみじみしたものです(笑)。


…私の懐古話が過ぎました。(左/上)は読書灯・室内の空調ほかコントローラー、(右/下)は通路上のスペースを使用した荷物置き場です。
最後までほぼ原形を保っていた>>24系「出雲」のそれとは異なり、こちらはツマミやコートかけが金色のものに交換されています。
今の感覚だとバブリーというか、成金趣味というか(殴)…いずれにせよ「お上品」な感じではないように見えますが、それもノスタルジーの一つとして楽しめるポイントでした。


室内のテーブル類(左/上)とナンバーロックのアップ(右/下)。「シングルデラックス」の鍵はナンバー式となっていました。
B寝台「ソロ」


変わってB寝台「ソロ」です。「ソロ」は個室部分が2階建てで、ご覧のように小窓が互い違いに並ぶ外観となっています(左/上)。


入口(左/上)と通路(右/下)の様子。入口は、ガラス戸による自動ドアでした。
B寝台「ソロ」下段


B寝台「ソロ」の様子。個室全景(左/上)と、ベッドのアップ(右/下)になります。
寝台幅は70cm、個室内に食い込む上段の張り出しによる圧迫感など、正直言って“広々”とは程遠い室内でした。
しかし、「鍵のかかるプライベート空間が、開放型B寝台と同じ料金で手に入る」というお買い得さがウケたのか、「はやぶさ」「富士」「さくら」に限らず、ブルートレインの中では「一番人気」と言っても過言ではない個室だったように記憶しています。
B寝台「ソロ」上段


上段寝台は階段が室内にあり、天井も湾曲していることから、ちょっとした「屋根裏部屋」のような雰囲気でした。(左/上)が個室内の全景、(右/下)が寝台のアップです。
下段の窓は単なるカーテンでしたが、上段は完全遮光タイプのブラインドがついていました。上段の方が、ホームの照明や朝方の日光の影響を受けやすい故の配慮と思われます。


通路上のスペースを利用した荷物置き場(左/上)と、空調・アラームなどのコントローラー(右/下)。
枕元には電気スタンドのような形状の読書灯が。ちなみにこの白熱電球の発熱はすさまじく、使っているだけでスタンドの“カサ”が触れないほど熱くなるシロモノでした。


足元にあるゴミ箱と灰皿の様子(左/上)と、「ソロ」の鍵の様子(右/下)。
鍵は、普通の建物でも見かけるようなシリンダーキーです。ルームキーホルダーには、テプラで車番(写真の場合2004)と部屋番号が記載されていました。
「ソロ」の鍵は、検札の際に車掌の方から鍵を受け取り~下車駅が近くなったら回収に来たor通りかかった車掌氏に返却、という形です。途中駅で降りる乗客がいる場合は、その度に車掌氏が車内を巡回されていました。
開放型B寝台 ①

最後に、編成中の大半を占めていた開放型B寝台の様子です。
こちらもJR九州へ引き継がれた後に内装のリニューアル工事を受けており、主な改造点は「通路をカーペット敷きに」「寝台モケットの変更」「カーテンの変更」などとなっています。


寝台の様子。(左/上)が下段、(右/上)が上段です。
寝台のモケット・カーテン類は、「ソニック」で見かけるようなポップな柄のものに交換されており、古めかしい寝台車の車内で異彩を放っていました。
開放型B寝台 ②


で、こちらが開放型B寝台の別の例です。
この車両もJR九州でリニューアル工事を受けていますが、こちらは上記の①と比較して、「寝台部分の化粧板がブラウン系」「寝台モケットもブラウン」「床はかーぺットではなくリノリウム」などの違いが見られます。
「富士」「はやぶさ」「さくら」では、開放型B寝台の内装はこの2種類に統一されていました。
概説
デビュー年:1971年
集中電源方式を採用した20系寝台車は編成ごとに電源車が必要であり、これが多層建て列車(一編成内に複数の行先がある列車)を運行する際の制約となっていた。
そこで寝台車の床下に小型の発電機を搭載した車両を数両おきに連結し、分散して電力を供給する「分散電源方式」を採用した寝台客車を開発することとなり、14系がデビュー。同時期に開発された12系をベースに、各種機器や寝台設備を近代化している。
1971年から増備が開始され、「さくら」「みずほ」「あさかぜ」などに導入された。しかし、翌1972年に発生した北陸トンネル火災事故を契機に、寝台車の床下に発電装置を設置する本系列は防火上問題があるとされ、一旦増備は打ち切り。代わって、本系列の車体・設備をほぼそのまま踏襲しつつ集中電源方式とした24系の増備に移行した。
その後、床下の発電機に防火安全対策を施した14系15形が1978年から再度製造された。
2000年代後半まで「はやぶさ」「さくら」などのブルートレインに使用されていたが、現在は完全に引退。