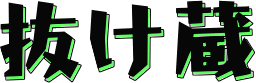103系3550番台「加古川線」


兵庫県の加古川~谷川を結ぶ加古川線。このうち加古川~西脇市間で運用されているのが、今回取り上げる103系3550番台です。
この103系3550番台は元・中間電動車からの改造という、ちょっと異色の経歴の持ち主です。全車両が加古川線への転用前に40N体質改善工事(→「備考」も参照)を受けているほか、105系にも似た貫通扉つきの先頭部を採用。装いあらたに、加古川線の‟顔”として日々活躍しています。
写真は加古川駅・西脇市駅でのカット。一見では103系の要素を感じにくい103系3550番台ですが、車内に入ると…それはこの先で追々説明していきましょう(笑)。さっそく車内に入ります。
【備考:40N体質改善工事の内容について】
JR西日本は、国鉄時代から引き継いだ車両にさまざまな体質改善工事(平たく言うと機器の更新と車内の改装)を施しながら長年使用してきました。当項で紹介する103系3550番台は、その中でも40N体質改善工事と呼ばれる工事を受けています。
これら工事の簡単な内容・背景などは>>103系3500番台「播但線」の項で紹介していますので、興味のある方はご覧になってみてください。
モケット

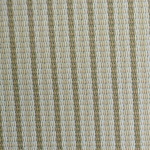

(左)座席 (中)カーテン (右)床
撮影日時・場所
撮影日時:2023年10月
場所:加古川線 西脇市駅 車内
備考
・説明の簡略化のため、40N体質改善工事を「40N」「40N車」と略して表記する場合があります。
・同じ兵庫県内を走る>>103系3500番台「播但線」の項も、(必要に応じて)併せてご覧ください。
普通車 車内

車内に入ります。
加古川線の3550番台は、転用前の2000~2001年に40N体質改善工事(以後、「40N工事」と略)が施されており、全車両がこの内装で統一されています。天井部分には工事前の吹出口や扇風機がのこっており、これだけでも40N工事の中では後期に改造されたのが分かります(→「備考」も参照)。
【備考:5年続いた40N体質改善工事の事情】
1996年から始まった40N体質改善工事でしたが、いざスタートすると思った以上に高コストなどの問題が露呈します。そのため、徐々に工事内容は簡略化されていきました。
内装的な観点から見ると、103系の40N体質改善工事車の内装は大きく分けて前期(試作車)・中期(1997~1999年)・後期(2000年~)の3パターンの内装があり、加古川線の103系3550番台は後期にあたります。
余談ですが、>>播但線の103系3500番台は全車が中期の内装です。ぜひ見比べてみてください。
座席


座席(左/上)と、座面部分のアップ(右/下)。
座席モケットは青ですが、これはJR西日本の103系でよく見られた仕様です。工事にあたってはモケットのみが張り替えられたようで、座面内部のバフッとしたスプリング感は健在でした。
車端部


車端部区画の全景(左/上)と、座席の様子(右/下)。
化粧板などの全面的張り替えのほか、貫通扉の交換・妻面(=連結面)の窓の廃止などが施され、改造前の面影はほとんどありません。
これ自体は40N車でよく見られる仕様ですが、同じワンマン運転を行う>>播但線の103系3500番台では妻面の窓が残っており、この違いの理由は気になるところです。
車端部 優先席(トイレつき区画)
※トイレ内部は後述


加古川寄りのクモハ102はトイレが設置されており、その様子(左/上)と向かい側の優先席(右/下)。
妻面の窓が埋められているのに加え、トイレに遮られて昼間でもかなり薄暗い空間になります。
運転席直後 優先席


西脇市寄り先頭車の運転台後ろは、ご覧の通りドア間全てが優先席になっています。全景(左/上)と、座席の様子(右/下)。
各車決まった側に優先席を配置するためと思われ、JR西日本ではすっかり見慣れた光景になりました。モケットの柄ゆえか、実際に見るとなかなかに圧巻ですが…(苦笑)。
その他の車内設備


天井の様子(左/上)と、荷物棚のアップ(右/下)。
照明・扇風機はカバーつきですが、それ以外の天井まわりは改造前の構造・雰囲気をよく残しています。


妻面(=連結面)の車番表記(左/上)と、座席下のアップ(右/下)。


窓まわり(左/上)と、つり革のアップ(右/下)。
窓のカーテンは窓一枚分のサイズになっており、両端のツメに引っかけることで3段階に高さを調節できます。空いているときならまだしも、混雑時に開閉するのはやや勇気がいりそうです。
運転台後ろ


運転台直後の様子(左/上)と、ドア脇の整理券発行機のアップ(右/下)。
運転台部分は3550番台化に伴って新規に製造されており、ほかの103系とは大きく雰囲気が異なります。
ドア


乗降用ドア(左/上)と、ドアボタンのアップ(右/下)。
ドア本体は、デビュー時から大きな変化はなさそうです。改造された時期ゆえでしょうか、ドアボタンは一昔前の風合いを感じます。
トイレ


トイレを外から見た様子(左/上)と、内部の全景(右/下)。
JR西日本の103系で初めて洋式トイレを導入したのが、この103系3550番台だそうです。洗浄方式は昔ながらの循環式で、トイレ内部には昔ながらの青い洗浄液のにおいが(なんなら向かいの優先席まで)漂っていました。
概説
デビュー年:2004年(103系3550番台のデビュー)
2004年の加古川線全線電化に伴ってデビュー。
2両編成4本の合計8両が投入された。播但線の3500番台とは異なり、3550番台は全車両が中間電動車からの改造となっている。
先頭車は貫通扉を備え、他の103系とは印象が異なっている。これは3550番台への改造時、2両編成を組むための制御電動車(クモハ103)が不足していたことに加え、当時は2両編成を併結した4両編成での運行があり、車内精算の都合で貫通形が必須だったという加古川線固有の事情によるもの。
全車が加古川線への転用前に40N体質改善工事を受けており、先頭部分を除いた内装や機器類の仕様はそれに準ずる。
加古川線の加古川~西脇市で運用。基本的に125系が使用される西脇市~谷川でも、検査や故障時などに代走で運用に入ることがある。2025年8月現在、定期運用の残る数少ない103系列の一つとなった。