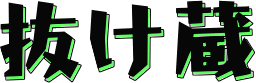目次
E4系「Maxとき」「Maxたにがわ」


デビュー当時の塗装。「MAX」のロゴも、先代となったE1系を受け継ぐデザインでした。
モケット



(左)普通車 (中)カーテン (右)床材
撮影日時・場所
撮影日:2020年3月23日(※一部除く)
撮影場所:「Maxたにがわ」181号 ガーラ湯沢駅 車内
備考
特にありません。
普通車1階 全景

続いて1階席に入ります。
1階席は全ての号車がこの内装で統一されており、自由席・指定席関係なく2+3アブレストの車内です。自由席では、乗り慣れた人は1階席に直行するらしく、取材時も3+3配置の2階席よりこちらの方が混雑していました。
座席モケットは明るいベージュを基調としており、座席部分が通路より一段高い「ハイデッキ構造」が採用されているのを除けば指定席用途の2階席の色違いのような内装でした。


車内を後ろから見た様子(左/上)と、天井(右/下)の様子です。
天井の化粧板、デッキと客室の仕切はいずれも黄色。照度の高い照明も相まって、車内は夜間やトンネル走行時でもかなり明るく保たれていました。
普通車1階 座席


2人がけ席の様子。写真(左/上)が一般席、(右/下)が車端部の様子となります。
「普通車2階席 指定席」で紹介した座席のモケット違いで、設備的な差はありません。


で、3人がけ席の様子。例によって一般席(左/上)と車端部(右/下)です。
(2階席にも共通する話ですが)窓枠部分の中央には張り出しがあり、缶飲料やペットボトル程度なら置けるようなテーブルが確保されています。もっとも、この1階席ではそもそも窓枠の位置が非常に高く、使い勝手としてはイマイチでしたが…(苦笑)。
普通車1階 座席正面


座席を正面から見た様子。(左/上)が2人がけ、(右/下)が3人がけです。
普通車1階 車内設備


車内をあえて斜め撮りしてみました(左/上)。座席と比べて、窓がかなり高い位置にあるのがお分かりいただけるかと思います。
(右/下)は通路の様子。座席は通路より一段高くなっている「ハイデッキ構造」となっています(先述)。
2(10)号車 普通車1階FL


2(10号車)の車端部は客室となっており、見ての通り1階席と同じ座席が3列展開しています(左/上)。
この区画、ネット上では「平屋」「車端部」などいろいろな呼び方をされているようでしたが、正式名称は「フラットシート」だそうです。車内の案内はこれを略して「1階FL」と表記されていました(→「備考」も参照)。
【備考;フラットシートの指定席券事情】
写真の2(10)号車は「Maxとき」「Maxたにがわ」では自由席として使用される号車ですが、車いす対応区画を兼ねた(基本的に)指定席の6(14)号車にも同様の1階FLが存在しました(後述)。
指定席でこの区画を取ると切符上に「Maxとき〇〇号1階FL」などと印字されます。


車内を反対から見た様子(左/上)と座席の様子(右/下)。
デッキ寄りの一列は、客室とデッキの仕切扉位置の関係で2+2配置となっており、その直後の3人がけ通路側は東京方面の上り列車においてテーブルがなくなります。その代替として、該当の区画には衝立を兼ねたテーブルを設置。もっとも、座席からは遠くテーブルは狭く…と、およそ「代替」と言うにはやや寂しいのは否めません。
どちらかというと、衝立を立てることで写真(右/下)通路側の利用者のテリトリーと、通路の動線が干渉するのを防ぐ意味合いが強かったのでしょう。
6(14)号車 普通車1階FL 17A・17B席 車いす対応区画


またしても1階FLの車内ですが、こちらは車いす対応設備を備える6(14)号車の様子。こちらは車いすでの利用に配慮して、2+2配置として通路幅を確保しています。
妙に車内が広く見えるような気がするのは、2+3配置が基本の車内に、普通席サイズの座席を2+2配置で並べているためでしょうか。


車いす対応区画は6(14)号車の17A・17B席となっており、写真(左/上)が全景、(右/下)がリクライニングと座面スライドを展開した様子になります。
基本的な見付は1階席のそれに準じていますが、車いす対応ということで、両端のひじ掛けが上がる・車いす固定用のベルトがあるなどの違いが見られます。


通路側のひじ掛けを跳ね上げた様子(左/上)とひじ掛けのアップ(右/下)。


座席番号表記(左/上)と1階FL部分を外から見た様子(右/下)。
車いす対応ということで、乗降用ドアも一般のものよりやや広く作られています。
5(13)号車 AEDコーナー


5(13)号車は、かつての公衆電話スペースを転用したAEDコーナーが設けられていました。
かつて「公衆電話利用の案内」が入っていたところにはAEDや人工呼吸、胸骨圧迫などのやり方を示した紙が入っており、元・公衆電話スペースの設備が思わぬ形で役に立っているようです(→「余談」も参照)。
【余談:かつてあった公衆電話とその後】
公衆電話はかつて2(10)、3(11)、5(13)、7(15)号車にありましたが、最末期は
・3(11)・7(15)号車…公衆電話あり
・5(13)号車…AEDコーナー
・2(10)号車…電話機を撤去してフリースペース化
となっていました。
※2つ先の項目より、トイレ内部の写真が含まれます。
廊下・洗面台


以降は廊下・洗面台・トイレなどの設備を一挙に紹介していきます。
廊下(左/上)と洗面台(右/下)の様子。洗面台本体は、自動水栓・ジェットタオル・ハンドソープが一体化したものが採用されていました。
※次の項目より、トイレ内部の写真が含まれます。
トイレ


続いてトイレ内部。男子小用トイレ(左/上)と男女共用トイレ(右/下)です。
写真はP19編成で撮影していますが、ネット上を見ているとブルー系の男女共用トイレもあったようです。編成や製造時期による個体差でしょうか。
5(13)・8(16)号車 車いす対応トイレ


5(13)号車と8(16)号車のトイレは車いすでの利用に対応しており、内部や入口開口部が広く取られています。
その他、おむつ交換用と思われるベビーシートも設けられており、写真(右/下)がその展開状態。ベビー“シート”というのが公式の呼称のようですが、実質的にベビー“ベッド”と言っても過言ではない大きさでした。
なお、5(13)号車は普通車、8(16)号車はグリーン車ですが、トイレ内部の設備は同一です。
目次
概説
デビュー年:1997年
E1系の改良型として1997年にデビュー。
先に登場していたE1系と比較して、省エネと輸送力の両立を図るため、車体はアルミ合金製となっている。また、E1系は12両編成だったが、本系列では他形式との併結運転も考慮し、汎用性の高い8両編成で登場した。
8両編成ながら定員は817名。16両編成での定員は1634名となっており、これは高速鉄道では世界一。
またE4系の中でもP51・52編成は、北陸新幹線への入線も考慮して急勾配での走行に対応しているほか、P81・82編成はこれに加えて60Hzにも対応しており、軽井沢より長野寄りへの入線も可能。
これらの編成は、一時期「Maxあさま」として軽井沢~上野・東京間の臨時列車に使用された実績がある。
登場時から東北・上越新幹線で使用されていたが、最高速度が240km/hであることから2013年をもって東北新幹線の運用からは撤退した。
当初は2016年に引退予定だったが、上越新幹線向けの後継車両の導入が進まず2019年に延期されていた。しかし、同年10月の令和元年東日本台風により、本来本系列を置き換える予定だったE7系10編成が水没して使用不能になったため、2021年10月まで使用された。
引退後は全車が廃車されたが、このうちP1編成の先頭車(新潟・盛岡寄り)が新津鉄道資料館に保存されている。