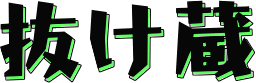201系 – 大阪地区「大阪環状・大和路・桜島線」


首都圏からオレンジバーミリオンの201系が消滅して久しいところですが、JR西日本では201系が2010年代後半まで主役級の活躍をしていました。
写真は深夜の桜島駅で発車待ちの201系。吹田総合車両所・森ノ宮支所に在籍し、桜島線はもとより大和路線、大阪環状線などで活躍。最新の323系に混じって、大阪地区の輸送を支えていました。


桜島線は沿線にユニバーサルスタジオジャパン(以後USJ)を抱えることから、そのUSJにちなんだラッピングが施された編成も2編成存在しました。
かつては同種のラッピングが103系に施されていましたが、森ノ宮の103系亡きあとは201系にお鉢が回ってきた、ということのようです。


行先表示(左/上)と車体番号の表記(右/下)。
行先表示は全てLED化されていたほか、車体番号の表記(右/下)も体質改善工事時にJR西日本書式のものに変更されています。
モケット


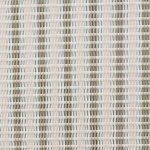
(左)一般席 (中)優先席 (右)カーテン
撮影日時・場所
撮影日:2018年4月23日
撮影場所:桜島線 桜島駅 車内
備考
特にありません。
車内全景

というわけで車内に入ります。
車内は化粧板の総取り換えなどが施されており、JR西日本の車両でよくみられるベージュを中心とした内装でした。
座席


座席(左/上)と、座面のアップ(右/下)。
座席そのものはデビュー当初から大きく変わっておらず、座席の両端の仕切・モケットが交換されている程度です。座ると腰がバフッと沈む、いわゆる昔ながらの座り心地もそのままでした。


車端部(左/上)とその座席(右/下)の様子。
体質改善工事後も、連結面の窓は固定化されて残っているのが特徴です。JR東日本の201系は後年この窓は埋められていましたが、このあたりは会社ごとの考えの違いでしょうか。
優先席 車端部


変わって優先席区画の全景(左/上)と、座席のアップ(右/下)。
座席モケットはJR西日本の共通柄になっています。
優先席 運転台後部


運転席後ろの優先席全景(左/上)と、座席のアップ(右/下)。
この区画は、ドア間の7人がけがまるっと優先席になっています。桜島線を基準にした場合西九条寄り、関西本線基準の場合はJR難波寄りの先頭車がこの仕様。同種の座席は、和田岬線などほかの車両でも見られたので、これがJR西日本の“共通仕様”だったようです。
各種車内設備


天井(左/上)と網棚(右/下)の様子。
天井は2本のラインデリアとクーラーが貫く構造ですが、これはデビュー当時からのものです。また、網棚も文字通りの“網”棚がまだまだ頑張っています。


座席両端の仕切のアップ(左/上)と座席下の様子(右/下)。
仕切の色は体質改善工事に変わっているようで、全体のカラーに合わせたものになっています。


つり革(左/上)と乗降用ドア(右/下)。
JR西日本車両のつり革は、最新の225系などを含めて今でも丸形が主流です。
車両概説
デビュー年:1979年
国鉄時代に大量増備された103系の後継車として1979年に試作車が登場、1981年より量産が始まった。
車体は103系から引き続いて鋼製が用いられ、基本的な車体構造は大きな変わりはない。しかし、抵抗制御に代わる省エネルギーな制御方式として、当時の国鉄としては初のサイリスタチョッパ制御、電力改正ブレーキを取り入れたのが特筆される。これにより、従来の101・103系と比較して走行時の消費電力カットを実現した。
ただし、当時はサイリスタチョッパ制御の制御回路が非常に高価であったことや、分割民営化直前の国鉄の財政事情などが重なり、103系を完全に代替するには至らなかった。その後の製造は、コストパフォーマンスの観点から201系をさらに進歩させた205系へ移行している。
JR東日本からはすでに引退しているが、JR西日本では現在も使用されている。
本項では、JR西日本の吹田総合車両所森ノ宮支所に配置され、大阪環状線、大和路線、桜島線などで活躍していた201系を取り扱う。