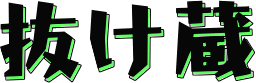目次
E4系「Maxとき」「Maxたにがわ」


先頭部を真横から見た様子(左/上)と、ガーラ湯沢駅で肩を並べる2本のE4系(右/下)。
高速走行時の騒音対策やトンネル微気圧波現象に対応する形で、先頭部は11.5mにも及ぶロングノーズとなっています。
モケット



(左)普通車 (中)カーテン (右)床材
撮影日時・場所
撮影日:2020年3月23日
撮影場所:「Maxたにがわ」181号 ガーラ湯沢駅 車内
備考
特にありません。
1~3(9~11)号車 普通車2階(自由席用途)

Maxが「総二階建て」を採用した理由に、当時急増していた新幹線での通勤輸送を見据えた“定員確保”があります。その概念は車内設備にもしっかり反映されており、(先代のE1系から引き続いて)自由席として使う前提の号車の2階席は3+3配置を採用していました。
写真がその「自由席前提」となる1~3(9~11)号車2階の車内。リクライニング、座席間のアームレストなどはバッサリ切り捨てられており、あくまで短距離での普段使いに的を絞った設計となっているのが特徴です。


車内を反対から見た様子(左/上)と、比較用にかつて喫煙自由席だった1(9)号車の様子(右/下)。
元・喫煙車の荷物棚には、例によって空気清浄機の跡が残っています。
【備考:3+3配置が「指定席」となったこともありました】
この車両は「自由席」での運用が“あくまで前提”ではあるものの、最繁忙期の臨時列車を中心に“指定席”として発売されたことが何度かありました。
この場合、横一列で6人目となるF席は販売されず、少しでも座席に余裕を持たせていた(というか、単にマルス側のシステム改修が面倒だったからという理由が大きそうですが)ようです。
しかし、結局片側は3人・もう片側は2人で使用するので、どうしても左右での“不公平”は拭えませんでした。
そうでなくても2+3配置の普通席と同じ料金でリクライニング無し・狭い横幅というのはあまりに設備の格差があり過ぎたためか、2000年代中盤を最後に全車指定席での運用は消滅しています。
1~3(9~11)号車 普通車2階(自由席用途) 座席


では座席の様子。(左/上)が真横から、(右/下)が正面から見た様子です。
リクライニングや座面スライドなどは一切なく、言ってしまえば単なる「回転式クロスシート」です。背もたれはかなり張りが強く、身体に合わないと快適性が今ひとつな感は否めませんでした。
不必要に沈み込む座面と、背中にゴツゴツと当たる背もたれのおかげで、実際に座ると全く落ち着きません。新幹線の居住性としては、お世辞にも良いとは言えない気がします。


座席番号の様子(左/上)。鉄道車両で全国的に見てもE1系とE4系にしかない「F席」がここにあります。
(右/下)は両端のひじ掛けのアップ。よく見ると、内部にヘコみがついています。この座席、回転時はひじ掛けはそのままに座席本体だけがグルッと回る構造なのですが、このヘコみは座席が回転するためのスペースを確保するためのもの。それと同時に、座席の横幅スペースの拡張にも寄与しています。
これによる拡張幅はせいぜい数cm程度ですが、それでも満席時(や隣に大柄な人が座ってきた時)には無視できない数cmとなるのでしょう。
1~3(9~11)号車 普通車2階(自由席用途) 車端部


1~3号車の2階は3+3配置ですが、車内とデッキの仕切扉は(大多数を占める)通常の2+3配置を前提とした位置に配されています(左/上)。そのため、車端部の区画は見ての通り2+3配置となっており、この車内で唯一となる2人がけ席が見られるのが特徴です(右/下)。
写真がその様子。2人がけとは言っても、3+3配置の座席を、単に2人がけに縮小しただけ。2+3配置の2人がけと比較して、横幅が確実に狭いのは否めません。


で、2人がけ直後の3人がけ席はこんな感じ(左/上)。
この区画の通路側は、列車の進行方向によってはテーブルがありません。その代わりとして、ひじ掛け下にカップホルダーが設けられています。写真(右/下)がそのアップですが、ご覧の通りテーブルの代わりにしてはやや寂しい感じでした(→「備考」も参照)。
【備考:カップホルダーはほぼ知られていなかった?】
このカップホルダーは非常に目立ちにくいところにあり、その存在が一般の利用者に認知されているのかは疑問なところでした。
取材時にいくつか弄ってみたのですが、展開にかなり力のいるカップホルダーが散見されたあたり、実のところはほとんど使用されていなかったようです。
4~6(12~14)号車 普通車2階(指定席用途) 車内全景

代わって4~6(12~14)号車の普通車2階席の様子。
「指定席」前提の区画で、車内は他の新幹線と同じ2+3配置です。先代のE1系では、同じ2階の普通席でも自由席と指定席で座席モケットが異なっていましたが、E4系では普通車2階席全てがパープル系で統一されていました。


車内を反対から見た様子と、比較用にかつて喫煙車として使用されていた4(13)号車の様子。
なお、編成によっては空気清浄機そのものが撤去されている車両もあったようです。
4~6(12~14)号車 普通車2階(指定席用途) 座席


では座席の様子。まずは2人がけ席からご覧いただきます。写真(左/上)が一般席、(右/下)が車端部の様子です。
今日JR東日本ではすっかりお馴染みとなった感のある座席ですが、本格採用したのはこのE4系が初でした。細かい違いはありますが、E4系のほか200系リニューアル車、E2系1000番台などに導入され、1990年代後半~2000年代前半にかけて一大勢力を形成しています。


3人がけ席の様子。一般席(左/上)と車端部(右/下)の様子です。
座席回転時のクリアランスを確保するためか、中央の席が完全に垂直になっているのが特徴です。座席背面を見るとさらに分かりやすいのですが、まさに“直立”しており、リクライニング無しで座るとかなり無理な姿勢を強いられます(→「備考」も参照)。
【備考:シートピッチ980mmの3人がけ席が回転可能になるまで】
この「シートピッチ980mmで3人がけ席座席を回転させる」というのは、それこそ200系の時代から開発者の頭を悩ませてきたようです。
当初の200系は3人がけ席を「あきらめて回転不可にする」、200系2000番台では「両端の肘掛は固定、座席本体のみ回転」することで解決。その後、E4系やE2系1000番台では、このように「3人がけの中央席を直立にして回転幅を確保」しています。時期によって、方式は違えど“苦肉の策”が積み重ねられてきた、ということなのでしょう。
なお、今日のE5系やE7系では普通車でも(原則)1,040mmが確保されており、座席の角度を調整しなくとも回転幅が確保できるようになっています。一般の人にはどうでも良いことでしょうが、3人がけ席に隠された“ドラマ”と言っても過言ではないポイント(大げさ)なので紹介してみました。
4~6(12~14)号車 普通車2階(指定席用途) 座席正面


座席を正面から見た様子。(左/上)が2人がけ、(右/下)が3人がけです。
どことなく安っぽさを感じるのは、妙に細いアームレストのせいでしょうか…(苦笑)。
普通車2階 通路2種


自由席区画(1~3号車:左/上)と指定席区画(4~6号車:右/下)の通路をそれぞれご紹介。
3+3配置と2+3配置なので比べるまでもないのですが、通路幅は指定席区画の方が広くなっています。自由席は、大人2人が姿勢を変えてやっとすれ違えるか程度の幅しかありません。
ガラガラな時ならまだしも、大荷物の利用者が多いスキーシーズン中の「MAXたにがわ」ではいろいろ大変なことになっていただろうと、撮影しながら感じた次第です(他人事)。
1~6(9~14)号車 普通車2階 共通の車内設備ほか


天井の様子(左/上)と窓上に備わるコート掛けの様子(右/下)。
照明は白色による直接照明で、夜間でもかなり明るい車内になります。


荷物棚の様子(左/上)と普通車指定席区画における座席とデッキ仕切の様子(右/下)。
自由席のそれと比較すると、やっぱりこちらの方が全体的に(見た目で)“すわりが良い”気がしますねぇ。
普通車 デッキ


デッキの様子(左/上)。乗降用ドアやエレベーター回りの化粧板は、グリーン車が緑系なのに対してこちらは青系となっています。
また2階・1階へつながる階段はスペース確保のためらせん階段となっており、天井もそれに合わせた形状となっています(右/下)。


車内販売ワゴン用のエレベーター(左/上)とらせん階段のアップ(右/下)。
手すりやステップには黄色いものが使用されており、利用者への注意喚起とともに視覚上のアクセントになっているようにも感じます。
5(13)号車 売店跡


5(13)号車には車内販売の基地を兼ねた売店があります。
かつてはショーケースにドリンクや弁当が所せましと並べられ、ちょっとしたキヨスクと遜色ないレベルだったのですが、末期は単なる車内販売の基地となっていたようでした。
なおTwitter(当時)での目撃情報によると、車内販売が乗務する列車で(ワゴンが動けないレベル)の混雑時など、極めてまれに売店として使用される場合もあるにはあった模様です。
>>このページは3ページ構成です。次は>>普通車1階席・トイレ・洗面台 編 です。
目次
概説
デビュー年:1997年
E1系の改良型として1997年にデビュー。
先に登場していたE1系と比較して、省エネと輸送力の両立を図るため、車体はアルミ合金製となっている。また、E1系は12両編成だったが、本系列では他形式との併結運転も考慮し、汎用性の高い8両編成で登場した。
8両編成ながら定員は817名。16両編成での定員は1634名となっており、これは高速鉄道では世界一。
またE4系の中でもP51・52編成は、北陸新幹線への入線も考慮して急勾配での走行に対応しているほか、P81・82編成はこれに加えて60Hzにも対応しており、軽井沢より長野寄りへの入線も可能。
これらの編成は、一時期「Maxあさま」として軽井沢~上野・東京間の臨時列車に使用された実績がある。
登場時から東北・上越新幹線で使用されていたが、最高速度が240km/hであることから2013年をもって東北新幹線の運用からは撤退した。
当初は2016年に引退予定だったが、上越新幹線向けの後継車両の導入が進まず2019年に延期されていた。しかし、同年10月の令和元年東日本台風により、本来本系列を置き換える予定だったE7系10編成が水没して使用不能になったため、2021年10月まで使用された。
引退後は全車が廃車されたが、このうちP1編成の先頭車(新潟・盛岡寄り)が新津鉄道資料館に保存されている。