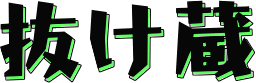キハ185系「剣山」


JR四国の‟顔”として華々しくデビューしたものの、後継車の登場で短い天下だったキハ185系。「うずしお」「むろと」などローカル特急をメインに活躍していましたが、2020年代に入ってから一気に撤退や列車の廃止が続き、気づけば「剣山」が唯一の定期運用となっています。
写真は、深夜の阿波池田駅に停車中の特急「剣山」運用時のカット。基本は2両編成のコンパクトな特急で、徳島~阿波池田を徳島線経由で結んでいます。さっそく車内を見ていきましょう。
モケット
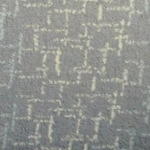


(左)座席 (中)カーテン (右)カーテン
撮影日時・場所
撮影日:2025年2月
撮影場所:徳島線 阿波池田駅 車内
備考
特にありません。
車内全景

車内の全景。
現在はほぼ全てのキハ185系がこの内装に統一されていますが、これは実は‟3代目”(→「備考」も参照)。座席モケットは淡いブルーを基調としており、床や仕切扉の色合いもあいまって小ざっぱりした雰囲気にまとまっているように感じます。


半室指定席を備える1号車(左/上)の全景と、車内を反対から見た様子(右/下)。
「剣山」の1号車は半室が指定席となっており、指定席部分は座席カバーの色を変えて区別しています。指定席は12~15番の4列16席だけなので「半室」とは名ばかり、実質「1/4室」程度ですが…(苦笑)。
【備考:キハ185系の座席事情】
キハ185系の座席はデビュー以来のR55Bが、改造を経ながらいまだに現役です。
座席モケットのカラーは、デビュー当時の明るいベージュ系からブルー・グリーン系(1990~1991年頃換装)を経て、2010年代以降のモケット張り替えで‟3代目”の現在の仕様になりました。座席肩部の手すりは‟2代目”の改造時に取り付けられたもので、‟3代目”にも塗色を変えてそのまま引き継がれています。
普通車


座席を見ていきます。指定席(左/上)と自由席(右/下)。
モケット換装・肩部の手すりの増設こそ経てはいますが、基本的にデビュー時からのR55(型番)が今でも現役です。この座席は、国鉄時代に製造された特急型車両をリニューアルする際によく使われたタイプで、2010年代ごろまでは全国的にあちこちで見ることができました。
現在(大掛かりに改造されていないプレーンな)R55が日常的に拝めるのは、この「剣山」がほぼ唯一の存在です。


座席を正目から見た様子。指定席(左/上)と自由席(右/下)です。
座席カバーは、指定席が青いナイロンのような材質の常備品、自由席は白い不織布のものがかかっていました。
普通車 車端部


車端部の様子。例によっ指定席(左/上)と自由席(右/下)です。
運転台直後のデッキには仕切りに窓が入っており(左/上)、窓越しではありますが前面展望が望めます。「剣山」の徳島方面行ではこの区画が指定席になる(1号車15番A・B席)ので、興味のある方は窓口や券売機などで指名買いしてみると面白いかもしれません。
なお、阿波池田方面行きでは自由席が先頭になるため、始発駅で早めに並ぶことになります(苦笑)。


車端部のテーブル全景(左/上)と、支え棒部分のアップ(右/下)。
テーブルを引き出す際は上に持ち上げるだけですが、収納時はテーブル下のつっかえ棒をズラす→長い方の金属棒を真ん中で引き上げる→テーブルを収納という、やや複雑な工程が必要になります。
初見だと迷うこと必至で、私の取材時もたたみ方が分からないのかガチャガチャやっているうちに下車駅に到着~そのまま降りて行った方がいらっしゃいました。説明書きのシールくらいはあっても良いように感じます。
車内設備


天井(左/上)と、座席上の空調吹き出し口・座席番号・荷物棚などのアップ(右/下)。
キハ185系は製造コストをおさえる観点から、空調は全てバス用の既成部品を採用。天井の・座席上の吹出口は、どちらも(キハ185系が開発された1980年代後半の)バスでも見られるもので、このちぐはぐな感じがキハ185系の面白いところと言えそうです。


窓間のダクト(左/上)と、通路の様子(右/下)。
各車両8列目・9列目(車両により7番)の間には恐らく空調のダクトがあり、その脇の座席番号脇には「↓」のシールが貼られていました。隣の号車も見たところ、ダクト脇の区画(そちらは7番)にやはり赤い矢印が。
この赤い矢印が何を意味するのかは、取材中・帰宅後にいろいろ調べてみた限りでは分かりませんでした。利用者向けならもう少し分かりやすく書くでしょうし、何らかの業務的な印と思われますが…何なのでしょう?ご存知の方はぜひご教示いただけますと幸いです。


窓枠(左/上)と、車内の温度計のアップ(右/下)。
窓枠部分はフチ付きの金属製になっており、缶飲料程度なら置ける程度の幅が確保されています。車内には、こんにちすっかり見かけなくなった針式の温度計も残っていました。
客室とデッキの仕切扉


デッキと客室の仕切扉(左/上)と、扉に入っている縦長のプレート(右/下)。
(左/上)は指定席・自由席の合造車で撮影していますが、仕切扉上のプレートは自由席側は「自由席」(写真)、指定席側は「指定席」側を掲示していました。この手の”青と緑で座席を示すプレート”も、近年めっきり見かけなくなった気がします。
ドア・デッキ


デッキに移ります。全景(左/上)と、ドア脇のステップ部分(右/下)。
キハ185系は普通列車としての運用も考慮しているため、乗降用扉を広く取りつつ2枚の折戸を採用した結果、圧倒的に長いステップとなりました。
ちなみにドアエンジンもバスの汎用品を使っているとのこと。電車というよりバスの出入口っぽさをどことなく感じるのは、それも一つありそうな気がします。


デッキ部分の通路(左/上)と、「くずもの入れ」のアップ(右/下)。
「くずもの入れ」には「たばこのすいがら」に関する表記もあり、ノスタルジーを感じます。
洗面台


洗面台の全景(左/上)と、シンクのアップ(右/下)。
鏡は小ぶりの1面鏡で、実用重視といった雰囲気です。蛇口は「湯」「水」の二つがありますが、私の取材時は「湯」のレバーが撤去されており、冷水専用となっていました。カミソリ用のコンセントやコップ受けなど、国鉄型特急から続く‟伝統の設備”はひととおり持っています(→「備考」も参照)。
【備考:「剣山」のコンセント事情】
「剣山」の座席にはコンセントがないため、このカミソリ用コンセントが「剣山」車内で唯一のコンセントとなります。
私の取材時もここでスマホを充電している方がいましたが、車掌氏は特に何かするわけでもなく、漏電や盗難などは自己責任で利用黙認となっているようでした。
もっとも本来の使い方でない以上、車掌の方の‟裁量”の要素も多分にありそうです。何か指摘された場合は素直に従いましょう。
トイレ


トイレの全景(左/上)と、ベビーベッドのアップ(右/下)。
トイレだけえらく先進的ですが、それもそのはずで2020年代に入ってトイレのリニューアル工事が行われたためです。改造にあたって洗浄方式を真空式にしたほか、ベビーベッド・ウォームレットの設置など、最新型の車両とそん色ない設備になりました。
見ての通り、改造から間もないためか非常に清潔です。ここまでやるなら、上述の洗面台も一緒にリニューアルすればよかったのに…と全く思わないわけではありませんが…(苦笑)。
概説
デビュー年:1986年(車両)
四国向けへの特急車両として1986年にデビュー。
四国エリア内に当時多く残っていた急行列車・急行型車両の特急化を目論んだものであり、四国内の輸送事情に合わせて短編成が組める設計としたのが特徴である。それまでの特急型気動車は、食堂車やグリーン車も含めた長編成を組成する前提での設計となっていたことから、最短2両編成での運行も可能な同車の設計思想は、当時は非常に斬新とされた。
国鉄末期の財政事情から、走行機器や内装(当時)の一部には廃車発生品を流用したほか、ドアエンジン・冷房装置にはバスの汎用部品を採用。キハ185系専用の部品を極力減らしてコストカットを図っている。
1986年のデビューとともに、「しおかぜ」(岡山~松山)に集中導入されたが、1990年には後継の2000系導入により早くも余剰となり、うち20両がJR九州に売却された。
2020年代に入ってからは「うずしお」(高松~徳島)、「むろと」(徳島~牟岐)、「剣山」(徳島~阿波池田)で運用されていたが、2025年3月改正で「うずしお」からは撤退、「むろと」は列車自体が廃止されたため、2025年6月時点では「剣山」が唯一の定期特急運用となっている。