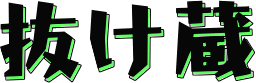富山地方鉄道14760形


富山地方鉄道が1979年に自社導入し、現在に至るまで同社の主力車両となっている14760形。2025年現在で7編成が在籍し、これは>>10030形と並んで富山地方鉄道の鉄道線では最多勢力です。
写真は、深夜の立山駅にて発車待ちの様子。デビューから40年以上を経た今も、富山地方鉄道の全線で普通列車から特急列車までオールマイティーに活躍しています。さっそく車内を見ていきましょう。
モケット



(左)座席 (中)カーテン (右)床
撮影日時・場所
撮影日:2025年2月、2022年9月
撮影場所:富山地方鉄道線 立山駅 車内
備考
特にありません。
車内全景

車内の全景。ドア間は転換クロスシートが展開しています。
かつて座席は進行方向向きにセットされていたのですが、2024年初頭から常時ボックスシート状態でセットされるようになりました。
折り返し時の手間を省くためなのかは不明ですが、同様の措置は>>10030形や>>16010形でも行われています。


参考として、進行方向向きにセットされていた時代の写真(左/上)と天井のアップ(右/下)。
常時ボックスシート状態への移行と相前後して、シートカバーも全て撤去されています。これもコスト削減の一環でしょうか。後述しますが、座席カバーのあったところだけ妙にモケットがきれいだったりします(笑)。
座席


では座席の様子。以後、比較用に現在の様子(左/上)とシートカバーの撤去前(右/下)の様子を併せて紹介していきます。
一見では単なる転換クロスシートですが、背もたれの転換にあわせて座面がシーソーのように傾くという、凝った仕組みが導入されています。これにより着座時にヒザより腰が低い位置にくるため、居住性はかなり良い印象でした。
もっとも富山地方鉄道、走り出すとそれなりには揺れるのですが…(苦笑)。


続いてドア脇の座席。
例によって、現在の様子(左/上)とシートカバーの撤去前(右/下)の様子です。ドア脇はパーティションに合わせてクッションの形状が異なっていますが、それ以外大きな差はありません。
よく見ると元・シートカバーがあった場所だけ、明らか色が濃くなっているのがお分かりいただけるかと思います。恐らく元々はこんな色だったのでしょう。
第1~4編成:車端部


第1~4編成の車端部はロングシートとなっています。現在(左/上)とシートカバーの撤去前(右/下)の様子。
座席カバーは波型タイプのものが採用されていました。かつては直線型の座席カバーもあったようですが、それについては私は撮影し損ねています。


第1~4編成の車端部はロングシートとなっています。現在の様子(左/上)と、シートカバー撤去前(右/下)です。
座席はおおよそ6~7人がけのようですが、私が取材した際は5人がけ程度で使用されていることが多かったように記憶しています。
第5~7編成:車端部


14760形の車端部は、当初全車両がロングシートとなっていました。しかし、特急運用への充当機会が増えたことから、第5~7編成は特急用として車端部が転換クロスシートに換装されています。
こちらがその全景(左/上)と、座席のアップ(右/下)。座席自体は他と異なる(>>10030形に微妙に似ている)ほか、ロングシート時代の台座が窓側に残っているなど、改造車らしいポイントがあちこちに見られるのが特徴です。
ちなみに転換クロスシートとは言えども、この区画で“転換”できるのは中央の1列のみです。
【備考:過去には新幹線から持ってきた座席が搭載されていました】
かつて一部の編成の車端部は、クロスシート化に伴って0系新幹線の廃車から持ってきた簡易リクライニングシートが搭載されていた時期がありました。
これらは1997年のワンマン化改造に伴って順次撤去(運転台直後)または本項で紹介した転換クロスシートに載せ替えが行われ、2000年代半ば頃までに見納めとなっています。
ただ、第4編成(14767-14768)の車端部に限っては2010年頃まで簡易リクライニングシートが残存していました。理由は不明ですが、当時はファンの間でちょっとした“名物“として知られていたように記憶しています。
車内設備


荷物棚(左/上)と、通路の様子(右/下)。
荷物棚はポール式となっていますが、これはデビュー当初からの仕様だそうです。


座席指定番号のプレート(左/上)と、窓間のコートかけ(右/下)の様子。
座席番号プレートは、富山地方鉄道のクロスシート車でよくみられる設備です。なお、富山地方鉄道の座席指定列車は2025年現在、定期での運行はありません。


SOSボタン(左/上)と、車内の防犯カメラ(右/下)。
SOSボタンは通話式となっており、ボタンを押すと乗務員と通話ができる仕様のようです。
ワンマン機器


最後にワンマン機器を見ていきます。運転台直後の区画(左/上)と、ドア脇のカードリーダー(右/下)。
運転席後ろには運賃表(後述)と運賃箱を設置。かつてはこの区画にも座席がありましたが、1997年から施行されたワンマン化改造に伴って撤去されて現在に至っています。


運賃箱後ろのヒーター(左/上)と、運賃表(右/下)のそれぞれアップ。
この区画は単なるデッドスペースかと思いきや、奥に車いすのピクトグラムがありました。どうやら、実質的に車いすスペースとして活用されているようです。
(右/下)の運賃表脇には、よく見ると「ローレル賞1980」の銘板が。乗車した際にはぜひご覧になってみてください。
概説
デビュー年:1979年
富山地方鉄道の創立50周年記念事業の一環として、1979年にデビュー。
車体構造は10020形をベースにしているが、車体前面や側面に当時流行のデザインをふんだんに取り入れている。このような意欲的な設計が評価され、1980年に「鉄道友の会ローレル賞」を受賞。2025年現在も、運転台後ろにその銘板が掲示されている。
車内はドア間に転換クロスシート、車端部にロングシートを採用し、普通運用・特急運用どちらにも対応できる内装とされた。編成は2両だが、多客時やラッシュ時などは2編成を併結して4両編成で運用される場合がある。
1997年からワンマン化改造が施されたほか、本系列の特急運用の増加に伴って第5~7編成の車端部が転換クロスシートに交換されるなど、編成により内装の差異が出ている。
現在は富山地方鉄道の全線で、普通列車から特急列車まで幅広く運用。全列車でワンマン運転が行われているが、3両以上時には車掌が乗務してツーマンでの運航となる。このほか、本系列の増結車(2019年以前は10020形の増結車)としてクハ175が在籍しているが、2021年ごろから事実上の休車状態となっているようだ。