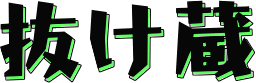目次
・普通車
・食堂車・運転席
0系新幹線「リニア・鉄道館」保存車


現在の新幹線の礎(いしづえ)を築き、高度経済成長期を支えた初代新幹線車両0系。このページでは2011年に愛知県にオープンした「リニア・鉄道館」に保存されている0系の車内を取り扱います。
同所ではビュッフェ車、グリーン車も含めた4両が保存されていますが、このうち車内が常時公開されているのは先頭車(21-86)と食堂車(36-84)のみです。


車体側面の様子(左/上)と行先表示(右/下)。
座席2列に一つの窓の「大窓車」かつ車体側面に非常扉があるなど、0系の中でも比較的初期に製造された車両です(→「備考」も参照)。
【備考:0系の「非常口」事情】
0系の中でも初期に製造された0・1000番台には、車体側面に非常扉が設けられていました。当時は新幹線の技術がまだ発展途上であり、「万一の非常脱出」が考えられることから設置されていたようです。
その後の新幹線の技術向上や安全性向上に伴い、1981年後半以降に製造された2000番台からこの「非常扉」は廃止されました。1000番台以前の車両にも非常口を埋める工事が行われ、この21-86も一旦埋められましたがリニア・鉄道館への移設時に“復元”されています。
のちほど非常口を内側から見た様子も紹介します。
モケット

(↑)普通席モケット
撮影日時・場所
撮影日:2024年4月・2019年6月(一部)
撮影場所:名古屋 リニア・鉄道館 館内
備考
撮影にあたっては、事前にスタッフの方に許可をいただき、一定の条件の下で撮影をしております。
また、「保存車の座席は着席禁止」という同館のポリシーに従い、撮影時は座面に触れないよう細心の注意を払って撮影しています。
車内全景

車内の様子。
0系の普通車の“象徴”といっても過言ではない、グレーとブルーのモケットをまとった転換式クロスシートがズラッと並んでいます(→「備考」も参照)。
【備考:この転換クロスシート、実は長生きだった】
この座席は0系のデビュー当時に採用されたもので、初期投入車(大窓車)のほか、マイナーチェンジを施した1000番台まで採用されています。
後年はリクライニングシートへの換装が進みましたが、一部の「こだま」用編成(JR東海所属)には1999年の引退まで転換クロスシートが残っていました。稼働期間は実に35年であり、まれなほど「息の長い座席」だったと言えそうです。
同じ座席が使用され続けた年数は、N700系が幅を利かせるようになった今でも破られていません。それだけ(当時としては)「完成」された座席だった、ということなのでしょう。


車内を後ろから見たところ(左/上)と天井の様子(右/下)。
背もたれだけを転換するため、座席背面にまで枕カバーが伸びているのが特徴です。
座席
座席への着席・付帯設備などの展開が禁止されているため、ややアングルが斜め気味の写真がありますがご了承ください。


座席の様子。2人がけの一般席(左/上)と車端部(右/下)になります。
座席単体としては「転換クロスシート」であり(先述)、リクライニング機構はありません。ただ、背もたれは最初からやや傾いており、(実際に着座はできないので推測ですが)座った時の掛け心地は存外ゆったりしていそうに見えました。


続いて3人掛け席です。例によって一般席区画(左/上)、車端部(右/下)になります。
写真では展開していませんが、通路側・中側ともにひじ掛け部分に引出式のテーブルが存在します。これにより、窓側のテーブルと併せて全席テーブル完備を実現。これも当時としては画期的だったそうです。


座席を正面から見た様子。2人がけ(左/上)と3人がけ(右/下)です。
一見すべて同じに見える0系の転換クロスシートですが、14次車以降は「座面が1席ごとに独立」「背もたれがやや高い」など微細なマイナーチェンジを施した「改良型」の座席に変更されています。この21-86は1971年に製造された12次車ながら、座席はなぜか「改良型」の方でした(→「備考」も参照)。
【備考:12次車に「改良型」の転換クロスシートが存在するのはなぜ?】
結局分かりませんでした。ご存知の方は公的な情報源を添えてぜひご教示いただけますと幸いです。以降は興味のある方だけどうぞ。
(以後無駄話)
この“ちぐはぐ”の理由は、公式や文献類など信頼できる情報源からは掴めませんでした。しかし、どうやら「引退後に載せ替えられた」というのが大方の推測のようです。上記の根拠として、
① 0系の現役時代に、この転換クロスシート間で載せ替えを行った記録や目撃がない
② 転換クロスシートから転換クロスシートへ載せ替えてもサービスアップになるとは言い難く、わざわざ手間をかけて載せ替える必要性が乏しい
③ 引退後の屋外での保存中にモケットが日焼けなどしてしまいやむなく交換した
などがあるようです。いずれも参考として記載します。
座席まわりの設備


肘掛部分のテーブルのアップ(左/上)と座席を背面から見た様子(右/下)。
窓側のテーブルは座席直後にまで迫っていますが、これはリクライニングのない転換クロスシートだからできる芸当でしょうか(笑)。


通路の様子(左/上)と、座席肩部の手かけのアップ(右/下)。
非常口


非常口のアップ(左/上)と、比較用に非常口部分を外から見た様子(右/下)。
非常口は、扉斜め上にあるコックを引いて開放する方式だったようです。最近“復元”されたわりには、妙に新しい感じが一切しないのは好印象です。
非常口のテーブル


窓側の小テーブルは基本的に固定式ですが、非常口部分のテーブルは折りたたみ式となっています。
非常口のテーブル(左/上)と、比較用にその他の区画のテーブル(右/下)。実際には操作していませんが、下の突っ張り棒を外すことで天板が下がるものと思われます。
車内設備


窓間のコートかけ(左/上)と荷物棚の様子(右/下)。
荷物棚は金属製のポール式のものが使われていますが、これはデビュー当時からとのこと。0系がデビューした1960~1970年代は、電車の荷物棚といえばまだまだ(文字通りの)“網”棚が主流だっただけに、当時はこういうところも斬新だったのでしょう。


座席番号のプレート(左/上)と「座らないでください」の表記(右/下)。
本件、詳しくは「備考」にまとめましたのでよかったら読んでみてください(→「備考」も参照)。
【備考:「リニア・鉄道館」のポリシーについて】
「リニア・鉄道館」の保存ポリシーから、座席への着席・引出式テーブルの展開・カーテンの展開は禁止されているため、写真では特に何もいじらないまま撮影しています。もちろん、当サイトでも上記ルールを全て遵守して撮影しています。
ときおり「このプレートがない席=座っても良い席」と勘違いしていると思われる方を見かけますが、実際に係員の方に私が聞いた限りでも、プレートがない席だからといって座って良い席ではありません。
0系新幹線を末永く保存していくためにも、間違いのないように気をつけたいところです。
デッキと客室の仕切扉


デッキと客室の仕切扉(左/上)と、仕切扉脇の号車プレート(右/下)。
この号車プレートは0系ならではの仕様でした。
乗務員室扉


先頭部分のデッキの乗務員扉が設けられています。
こちらの日本語表記は、他の車両でもよく見かける「乗務員室」ですが、英語表記は(定番の「CREW」ではなく)「運転士」を意味する「MOTORMAN」なのが特徴です。
このページは2ページ構成です。次は>>食堂車・運転席 編です。
目次
・普通車
・食堂車・運転席
概説
デビュー年:2011年(リニア・鉄道館での展示開始年)
2011年に愛知県にオープンした「リニア・鉄道館」に展示されている0系新幹線を取り扱う。
先頭車(普通車)である21-86は1971年製造で、製造から一貫してほぼ「こだま」で運用された。JRの分割民営化後はJR東海に所属し、1991年まで使用された。
その後はJR東海の浜松工場で保管され、時折同所の一般公開で展示される程度だったが、リニア・鉄道館における保存車に選定され、2010年に登場当初に近づける復元作業を経て現在に至っている。
他方食堂車の36-84は1975年に製造され、当初から「ひかり」で運用。民営化後はJR西日本に所属し、食堂車を組み込んだ最後の編成となったNH32編成に連結され1999年に廃車。その後はJR東海へ保存目的で譲渡され、リニア・鉄道館へのオープン時に同所へ搬入された。
普通車は保存のため座席への着席やカーテン類の展開は禁止されているが、内装は0系新幹線のデビュー当時に可能な限り近づけた仕様となっており、往時の雰囲気を感じられるようになっている。また、食堂車は一部区画のみが公開されている。
なお、リニア・鉄道館にはグリーン車とビュッフェ車も保存されているが、現在は一般公開されていない。